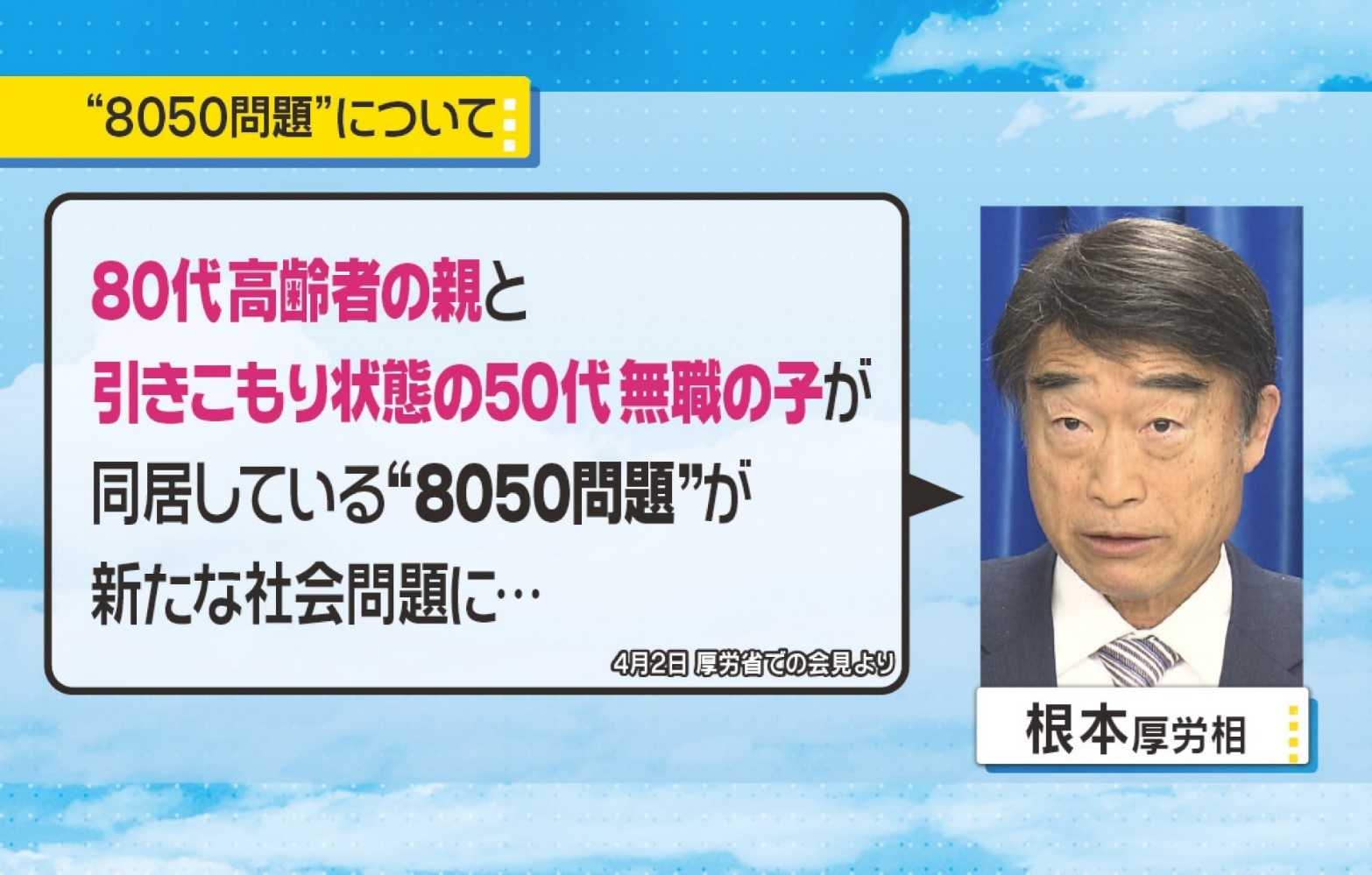ひきこもり高齢化 地方では|ひきこもりクライシス“100万人”のサバイバル|NHK NEWS WEB

一度、ひきこもりの状態になるとなぜ長期化するのでしょうか。 ひきこもりを考える際のポイントは特有の悪循環にあります。 ひきこもりの悪循環とは、人をひきこもり状態から抜け出しぬくくさせる構造のことです。 本人が抜け出したいと願っても、容易には抜け出せなくさせる構造がひきこもり事例の大半に共通して存在しています。 本来ならば、ゆっくりと心を休め、自分を見つめなおす豊かな営みであるはずの「ひきこもり」が、なぜ人を悪循環に陥れるのでしょうか。 それでは実際に、ひきこもりの悪循環の構造はどのような姿をしているのでしょうか。 理解の手がかりとして、まずひきこもり経験者の自己分析を紹介しましょう。 ひきこもりが自身の意図を超え、長期化してしまう様子をよく洞察した自己分析です。 語り手は神戸市に住む50代の男性で、高校時代から20代の終わりまでをひきこもり状態で過ごした方です。 小さな食堂を経営していますが、店は休みがちで長期休業することもよくあります。 彼は自身のひきこもり経験をこう振りかえりました。 「つまらない人生でした・・・・。 そう総括しなければならないことはつらいことですけれど、まぎれもない事実として僕のひきこもり人生は、つまらない痛恨の人生でした。 残すべきものも残すべき相手もいません」 自分がひきこもり状態に入った経緯について次のように説明しました。 僕のひきこもりは、ぬくもりを求めての逃避から始まりました。 怠け者のくせに、できもしない高望みをしたせいで、現実とのギャップに傷ついてしまい、現実社会に居心地の悪さを感じました、と・・・。 「ぬくもりって、たとえて言うなら冬の朝に感じる布団のなかの心地よさです。 そこへ逃避しようとすることが出発点でした。 でも、ぬくもりのなかへ一歩踏み出した瞬間、自分自身の罪悪感との闘いが始まるんです。 」学校へ行けなければならない、会社へ行かなくてはいけない・・・・自分自身の中に刷り込まれているそうした社会的規範や常識と呼ばれるものに、自分は背いてしまっている。 彼の罪悪感はそのような認識から生まれてきました。 「罪悪感からは孤立感が生まれました。 孤立感から不安感が生まれ、不安感は恐怖感につながっていきました。 そこには安住できないとわかって、外に出たい、何かしたいと思っても、身動きできないくらいに固く僕を縛りつけてきたものは、何よりこの恐怖感です。 他人の目が怖い、社会がとても怖い・・・・。 満足に泳げないのに暗い海を一人で沖へ泳ぎださなくてはならないときの感じ、といいますか・・・・。 理屈じゃない。 ただひたすら怖いんです。 」 恐怖感ゆえに動けなくなってしまう経験については、ほかにも多くのひきこもる青年たちが証言しています。 たとえば20代のある男性はそれを「歩くことをしらない赤ん坊が右足から先に出せばいいのか左足から先に出せばいいのかわからなくて、すくんで一歩も踏み出せない状態です。 」と表現しました。 この男性の話には、ひきこもりが生み出す不安感や恐怖感がひきこもり期間を長引かせ、ひきこもりが長期化してしまったことが外界への不安感や恐怖感をさらに強める、という悪循環の構造が見えます。 「こんなはずではなかったのに」という彼の実感は次のような言葉にも如実に表れています。 「心地よいはずだったひきこもりが実際にはひどく居心地の悪い世界につながっていて、袋小路か迷路のように脱出不能になっていました」 「ひきこもったことで、ちっぽけで虚弱な人間が自分自身と社会を相手に果てしなく格闘しなくてはならなくなりました。 逃避をしたはずなのに、逃げ場がないんです」ひきこもってはみたものの、社会との隔絶には成功せず、むしろひとりで社会と取っ組み合う状況に追い込まれてしまった、との訴えです。 ひきこもりをしている間にすることは自分で自分を否定し、破壊することでもあったと彼は言いました。 「ひきこもっている最中にひとりで繰り返すことは、自己批判であり、自己嫌悪であり、自己破壊です。 自分で自分をずたずたにしてしまう感じでした」 「若い頃にはひきこもりの正当性を主張しようと考えたこともあります。 でも負け犬の遠吠えだという思いはぬぐえませんでした。 悲しいことに、他の誰でもなく自分自身がひきこもりを肯定していないんです。 社会から逃げ出してひきこもりをしている人間は、ひきこもりからすら逃げ出したいのです。 それでも現実には、だれも僕にお前は不要な存在だとは言いませんでした。 言っていたのは僕自身です」・・・・。 彼は自分自身に「お前は不要な存在だ」と宣告していたのです。 ひきこもるという行為を誰よりも自分自身が正当と認められないからこそ、動けない自身の現実との間で深刻な葛藤が生じるのでしょう。 彼のこの告白は、なぜ罪悪感が不安感や外界への恐怖を生むのかという「理由」を説明しているようにも聞こえます。 自尊心が壊れ、自分が世界に存在することの意義を信じられなくなった状態にあっては、人は自身の姿を他者や外界に平常心でさらせるものではありません。 たとえ周囲の人から具体的な非難をあびなくても「まわりは自分のことを悪く思うのではないか」と思いこんでいるひきこもりの青年は少なくありません。 その人の行動を責めているのはおそらく内面化された社会規範であり、だからこそその人はひとりで際限なく自身を責め続けるのだと思います。 ひきこもることで「他人」と離れることはできますが、「自己」とまで離れることはできないからです。 まさに「逃避したはずなのに、逃げ場がない」というひきこもりの実情が、ここにあります。 これに関連して、ひきこもる人たちによく見られる感情の一種に恥ずかしさや引け目の感情がある、とわたしには思えます。 「いい大人が昼間にぶらぶらしていては近所の人に変に思われて恥ずかしい」「働いていないことがばれると嫌なので、親戚が遊びに来たとしてもずっと自分の部屋に隠れていたい」「いま何をしているのかと聞かれるのが嫌なので、知り合いからの電話には出たくない」と自分の思いを語る人が少なくありません。 他者の目から自分を隠すことで、揺らぎそうな自尊心を必死で守ろうとしている様子に見えます。 ひきこもりを恥ずかしいと思えば思うほど、人はひきこもっている事実そのものを隠したい心理に支配されがちです。 しかし、他者の目からひきこもりの事実を隠す手段は現状では、より深くひきこもることでしかありません。 そこは蟻地獄のような悪循環への入り口です。 「ひきこもりは甘えだ、ぜいたくだ」という偏見を周囲が強めれば強めるほど、人が蟻地獄から脱出できる可能性は低くなります。 わたしは、ひきこもる人たちの多くはむしろ一定の規範意識を持つ人たちだという印象を持っています。 彼らや彼女らは心のなかに「働かなければならない」「経済的に親に依存していてはならない」という意識を持っているように感じられます。 逆にもしこうした規範意識がなかっとしたら、実はひきこもりの悪循環構造も成立しないのではないか、とわたしは考えています。 ひきこもることにまったく規範的な引け目を感じない人がいたら、その人はおそらく罪悪感や孤独感による葛藤に苦しめられることもなく、「自分はだめな人間だ、恥ずかしい人間だ」という自尊心の著しい低下に陥ることもないはずだからです。 ひきこもる人たちが「自分はダメな人間だ、恥ずかしい人間だ」と判断するときの基準は、この社会で作り出されたものです。 当然ながら、同じ行動でも日本では「恥ずかしい」と思われ、他国ではまったくそう思われないという事態はあります。 たとえば障害者の自立問題に詳しい谷口明広氏は朝日新聞の座談会で、障害者の意識と社会環境の変化について次のように語っています。 「日本人は何でも自分のせいにする。 駅で階段を上がれないと歩けない自分が悪いということになります。 アメリカ人はエレベータがない駅が悪いというふうに考えます。 」 自分はダメだと決めつけてひきこもっている人と「大人のくせに働かずにひきこもる人など許せない」と憤っている社会人は、おそらく同じ規範意識を共有しています。 そうした共有の状況下では「規範そのものに無理があるのではないか」と疑う方向には意識が向きにくいともいえます。 さて、ひきこもりから抜け出しにくいわけとして考えられる別の理由に、ひきこもっている人が孤独な状態にあることもあげられます。 たとえば哲学者の鷲田清一氏は、著書で次のように指摘しています。 「自分のうちをいくら覗き込んでも、何がこれが自分だ、といえるようなものに出会えるわけではない。 (略)自己の同一性、自己の存在感情というのは、日常的にはむしろ、(眼の前にいるかいないかとは直接は関係なしに)他者によって、あるいは他者を経由してあたえられるものであって、自己のうちに閉じこもり、他者から自分を隔離することで得られるものではない。 他者から隔離されたところでは、人は自己を求めて堂々めぐりに陥っていく」(「聴く」ことの力・TBSブリタニカ) ノンフィクション作家の柳田邦男氏はひきこもりがちだった次男と向き合うなかで、この問題に直面していました。 次男の洋二郎さんはひきこもりがちな青年時代を送った末に、自殺しました。 柳田氏は次のように語ります。 「洋二郎は僕は誰の役にも立てない、誰からも必要とされないといっていました。 生きる意味の問題です。 「自分が生きて人生を作るなかでしか、その答えは出てこない。 答えは結果として出てくるんだ」と僕は言いました。 でもそういいながらジレンマに陥ってしまう感じもしていました。 世の中に出て行かないと、明確な答えは出てこない。 けれど彼の悩みは、世の中に出られないことなのですから」・・・・・。 孤独のかなで成長することの難しさです。 こうした孤独が長引けば長引くほど、「人との交流経験や社会経験のなさ」というハンディは重くなりがちです。 このことは、ひきこもる人たちが社会に一歩を踏み出そうとするときにしばしば、無視できない重荷となります。 ある長期間ひきこもりを続けている男性が言っていた「同世代の人がどういう服を着ているのかテレビ以外では見たことがなかった」というほどではないにしても、超えなければならないハードルは通常かなり高いのが現状です。 「どうやって他人と話せばいいのだろうか」「集団のなかでは一体どう過ごすのが妥当なのだろうか」「職場の上司や後輩とは、どう付き合うべきなのだろうか」「どの程度仲良く、またどの程度距離を置くべきなのだろうか」などと悩み、社会への入り口で立ちすくむ人たちが少なくありません。 孤独がもたらす影響については精神科医の斉藤環氏も著書で触れています。 ひきこもることで人は、挫折経験による精神的外傷から回復する機会を失ってしまうといいます。 それは「対人関係によって補われるはずの治癒の機会が奪われて」しまうことによるもので、そうなるとひきこもっていること自体が「外傷に等しい影響」を持ってしまうと氏は指摘しています。 これもまた「外傷が外傷を生み出していくような」悪循環のシステムなのです。 ここまでの話は主に、ひきこもる当人の内面の問題に注目してきました。 しかし、「ひきこもり特有の悪循環」には通常、周囲の家族も深く関係しています。 家族を含めた悪循環の構造について、精神科医の近藤直司氏はおおむね次のように説明しています。 青年のひきこもりは「(親をはじめとした)家族の不安や焦り」を呼び起こしやすいのです。 このまま子どもが外出しなかったらどうしようといった不安や、何とか早く就職してほしいという焦りです。 そうした不安や焦りのため家族は、本人につい「外出刺激」を与えがちになります。 車の免許を取りに行ってはどうかとか、アルバイトならできるのではないかと、外出や就労を促すことです。 しかしこれらの刺激は、しばしば本人の「劣等感・被害感」を強めるだけの結果に終わりやすいです。 実際には行動できないことが多いため、「親にもわかってもらえなかった」といった精神的な挫折体験に終わるのです。 劣等感や被害感が強まることによって、本人はますます深く「ひきこもり」状態に入っていきます。 その強化された「ひきこもり」を見て、親はさらに「不安や焦り」を強めてしまう・・・・。 わたしの支援経験に照らしても、この説明はかなり納得のいくものです。 逆に「親が外出刺激をやめたら子どもが部屋から出てくるようになった、親とコミュニケーションをするようになった」といった事例は枚挙にいとまがありません。 もちろん、すべての外出刺激がいけないのではありません。 親がまったく何の刺激もせず、自身の振る舞い方を点検することもしないという姿勢は、単なる放任と変わらないでしょう。 外出刺激は当人の心理的な負荷を増しやすいという仕組みを理解した上で、ではどのタイミングでどのように働きかけるべきかを検討していくのが基本です。 なお近藤氏は前述の悪循環のほかにも、二つのパターンの悪循環が見受けられると語っています。 ひとつは自分の問題に向き合うことを放棄した本人と「放っておいてやるのがいちばんいい」と考える親がペアになるパターンです。 ひきこもりが長期化している家族に見られやすいもので、本人は将来を考えると不安になるため、親は「問題を突き詰めていくと子どもを壊してしまうのではないか」という不安があるために、長期化するほど不安も増大する悪循環に入ってしまいます。 もうひとつは、「こうなったのは親のせいだ」と考える本人と「わたしのせいだ」と思い込む親がペアになるパターンです。 この場合、子どもは親の子育てが原因だと考えるため、ひきこもりが自分の問題だとは認識されにくいといいます。 医師の視点から見ると、いずれのパターンも援助を求めようという動機を持ちにくい点で共通しており、親子ともども社会的援助との接点を失って孤立の悪循環に入り込みやすい、と氏は警告します。 一方、関東自立就労支援センターは、親子間の認識のすれ違いに注目しています。 わたしたちは、ひきこもりの子を持つ親の多くが「そんなことをしていて社会に通用すると思っているのか」といった説教をしがちなことに目を向けています。 「社会代表のような説教のしかた」です。 そうした親に共通しているのは「お前はわかっていないからわたしが教えてやる」という認識でした。 他方、言われた側の子どもたちには「やはり親はわかっていない」という失望感が見られます。 そこには親子のすれ違いを見ることができます。 「ひきこもる子はわかっているのにできないから葛藤しているのですが、親は子どもはわかっているという事実に気づきにくいのです」 つまり子どもたちが「親はわかっていない」という言葉で表しているのは「僕がわかっているという事実を親はわかってくれない」との失望感なのです。 こうした経験が重なるうち、失望感が「わかってもらえるはずがない」という絶望感に変質してしまうのです。 親がよかれと思ってした説教が、親子間の心理的な溝を深めてしまうという悪循環です。 また子どもがひきこもった場合、親も地域とのかかわりをなくして孤立し、いわば家族ぐるみでひきこもりにはいってしまう傾向が強いです。 子どもがひきこもっていることを親類にも近所の人にも言いにくく、相談に乗ってくれる援助の場も少ないため、親たちも孤独に悩みがちになります。 特に母親は孤立に悩む傾向が強いです。 子育ての責任を一手に引き受けさせられる場合が多いためであり、そのうえ夫から「お前の育て方が悪いからひきこもったのだ」などと責められるようなものなら孤立感は倍増します。 「わたしが悪かったのだ」と自責して精神的にまいってしまう母親も少なくありません。 多くの親に共通して見られるのは、「子どもを社会に送り出すことが親の責務である」という考え方です。 だからこそ子どもがひきこもった場合、親は自身に「責務を果たせないダメな親」という評価を下すのです。 こうした自己評価の低さが「対人関係からの回避」に向かう傾向は、子どもの場合と同じです。 いろいろ話を聞いていますと、「親が態度を変えたらひきこもっていた本人が元気になり、家族とコミュニケーションをするようになった」という話や「親が亡くなったり病気で倒れたりしたら本人が外へ向けて動き出した」という話に出会うことがあります。 前者はかなり頻繁に出会う事例で、語られる場合も肯定的に語られることが多いです。 後者の話はまれにしか出会わない事例で、世間から「やはり親に寄生していただけではないか」と否定的な視線を向けられがちです。 しかしわたしは、どちらの事例も悪循環の構造が変化したことによる結果として、ある程度説明できると見ています。 家族ぐるみの悪循環のなかでは、家族の一人ひとりが何らかの「働き」をしており、そうした働きの総体としてある悪循環構造が成り立っている、と考えられます。 先にあげた「親が態度を変える」行為は、親の果たしていた働きに変化が起こることを意味します。 個々の働きに変化が起これば当然、構造全体にも(大なり小なり)変化が生じます。 本人が元気に変わったことは、そうした構造の変化によるものと考えられるのです。 同様に親が死亡することは、ある構造のなかで重要な働きをしていた構成員が欠けることを意味します。 そのことが構造全体に与える影響はきわめて大きいでしょう。 結果として悪循環構造が一種の機能不全に陥り、本人が抜け出しやすい環境が突如現れたのではないか、とも推察しうるのです。 ただし当然ながら、個々の「働き」が変わることは必ずしもプラスの変化につながるとは限りません。 ひきこもりの深刻化を招くような変化もありうるでしょう。 補足しておきますが、ひきこもりに特有の悪循環が見られるということは、かなり以前から多くのひきこもり援助者によって注目されていたことです。 それぞれの援助者がそれぞれの表現で悪循環的な構造の存在を指摘しています。 細部の違いはありますが、ひきこもりに悪循環が見られること自体は大方の共通認識になっているといっていいでしょう。 またわたしは、悪循環を形作る要素のひとつに、履歴書の「空白」問題を加えたいと思います。 ひきこもり期間が半年、一年、二年と長期化するにつれて空白は大きくなり、就職する際の難しさも増していく現実があるからです。 ここには、ひきこもりが長引くほど、職業社会への入り口は狭まるという社会ぐるみの悪循環の構造があります。 近年は不況も加わり、ひきこもり経験のある青年たちはきわめて厳しい条件下での再挑戦を強いられています。 ひきこもり状態の長期化は、心理や精神病理だけで説明のつけられる問題ではないのです。 青年たちの再挑戦がどれだけ社会的に保障されているか、青年が社会的に成熟していくための場が学校と会社以外にどれだけ用意されているかといった観点からの見直しが求められていると思います。 なお念のためですが、ここに示した悪循環の構造は必ずしもすべてのひきこもり事例に見られるものではありません。 ここに示した悪循環の構造は説明のためのモデルに過ぎず、現実のひきこもりのかたちは十人十色です。 ですから当事者の方々にはこのモデルを、自分が悪い流れにはまり込んでいないか自己診断するための一材料として利用してもらえばいいし、第三者の方々にはひきこもりが特定の問題青年や問題家族に起こる現象というわけではなさそうだとの認識に近づくためのひとつの手がかりとして利用してもらえばいいと思います。 ある現象を理解するには、それがこの社会でどの程度広がりを持つものなのかを把握する作業だ大事になります。 ですから「ひきこもりの人は全国に何人ぐらいいるのか」という問題を考えることには意味があります。 ただしひきこもりという現象は、広がりを数的につかむことがきわめて難しい現象でもあります。 その主な理由は二つあげられます。 まず明確な定義を作ることの難しさがあります。 現状ではひきこもりと非ひきこもりを分ける明確な線引きがありうるかどうかについてさえ、援助者の間で意見が分かれています。 また思い切って便宜的に線引きをするにしても、何をひきこもりとするかという定義が異なれば当然、人数も大きく変わってきます。 二つ目の理由は、実証的な調査を行うことの難しさです。 もしひきこもりの人数が明らかになることがあるとすれば、それは全戸を対象にした詳しい実態調査を行えた場合に限られます。 その場合も全国調査を実施できるとは思えないので、地域などを限定したうえで推定の全国値を出す手法が現実的です。 しかし実際には、この種の調査は個人のプライバシーに触れることなどから実施が極めて難しいです。 特に日本では、精神病の詳しい実態調査も満足に実施できていない現状があります。 つまりは当面、ひきこもりの人の実数が明らかになる見通しはほとんどないのです。 現在まではひきこもりの人が全国に何人いるかを把握していませんが、その調査をすること自体が現実にはほぼ絶望的なのです。 もし数的に把握できる可能性があるとすれば、それは本人や家族が援助の場に足を運んだ数としての「相談件数」だけでしょう。 この数字に一定の意味はありますが、「どこにも相談していない」という当事者・家族が少なくないことを考えると、その数字はひきこもりの実数とはかけ離れたものである可能性が強いです。 また相談件数をいくらさかのぼって調べても、ひきこもりの人が増えたという裏づけにはなりません。 たとえばわたしが新聞連載である保健所のひきこもり援助事例を紹介した後、その保健所には一ヶ月で約10倍の問い合わせが殺到しました。 報道などでひきこもり現象や援助の情報が知られれば知られるほど相談件数は増えるのです。 もし仮に相談件数が十年前より大幅に増えたとわかっても、それがひきこもり事例の増加によるものなのか、ひきこもり現象が知られたことによるものなのか、までは知りようがありません。 それゆえわたしは「ひきこもりの人が増えている」という言い方を使わないようにしてきました。 現在の人数も過去の人数も知りようがない以上、誰も「増えている」「増えてきた」という根拠を持っていないのです。 とはいえ、ひきこもりの実数に関する言及が今までなかったわけではありません。 毎日新聞は1994年5月29日付の朝刊一面トップでひきこもりを大々的に報じました。 「ひきこもる大人」という見出しの下に大きく「全国に1万人以上」という見出しが躍っています。 記事には「カウンセリングの専門家らの調査では、その数は全国で少なくとも1万人以上に上ると見られる」と書かれ、社会学研究者である森田洋司氏の「成人のひきこもりは1万人を超えているだろう」というコメントが紹介されています。 ただし記事では、なぜ1万人以上いると算出されたかについての具体的な根拠は示されていませんでした。 いずれにしても、1万人という数字は、当時の感覚としてはかなり衝撃的なものでした。 それから4年後、精神科医の斉藤環氏は著書「社会的ひきこもり」で、社会的ひきこもりの状態にある青少年の数について「実態は、調査がきわめて難しいためもあって、いまだに正確な把握はなされていません」としつつ、「一説には数十万人ともいわれている」と記しました。 同書では、誰がどのような根拠で算出した数字かについては触れていません。 2000年になると氏は、社会的ひきこもりの人の数についてテレビや雑誌で「わたしの推定では、ごく控えめに見ても数十万人、個人的印象からはとうに100万人は越えたと考えている」と発言するようになりました。 100万人以上という算出の根拠らしい根拠は示されませんでしたが、複数のマスコミや一部のジャーナリストがそのまま世間に紹介したことによって、この巨大な推測数値はあっという間に既成事実化しました。 しかし100万人以上とはどういう数字でしょうか。 先に述べたとおりひきこもりの人の実数は誰にもわからないので、100万人以上はいないと証明する根拠は誰も持っていません。 それでもわたしはこの数字への違和感を感じずにはいられません。 もし本当にひきこもりが100万人以上いるとすれば、その存在が社会に与えるであろう影響はあまりに甚大だからです。 斉藤環氏の見解によれば、ひきこもりの人のうち、不登校の経験者は約9割であり、不登校事例のうち、慢性的なひきこもり状態へ移行するのは約3割とされています。 ひきこもりが100万人以上存在するためには、90万人以上の「不登校経験者を持つひきこもりの人」が必要になる計算です。 ちなみに文科省によれば、99年度の不登校の子の数は約13万人でした。 このうち中学3年生は4万人台と見られ、その規模の子どもたちが毎年新たに不登校経験者として社会に現れてくることになります。 氏の見解に従えばそのうちひきこもりに移行するするのは3割、つまり1万人あまりです。 この規模の数字が一体何年積み重なると90万人以上という数字に近づくのか、わたしには疑問に感じてしまうのです。 また10年前には今の半分程度しか不登校の子どもがいなかったことを考え合わせるとき、この疑問はますます強くなります。 仮にひきこもりの推測総数を50万人に減らし、不登校経験者の割合を7割に落として計算しても、同様の疑問は消えません。 さらに言うと全国に100万人以上のひきこもりの人がいるということは、100万以上の世帯でひきこもりが起きていることとほぼ等しいことになります。 ひきこもりが起きている世帯の構成人数は、ほとんどの場合が3人以上であるとみていいと思います(両親らと同居している場合がほとんどだからです)が、国勢調査に基づく総務省の最新統計によれば、3人以上の世帯数は全国で約二千二百五十万世帯しかありません。 そのうち100万近い世帯がひきこもりに悩んでいるという状況は、発生率が高すぎるように思えてわたしには想像しがたいのですが、いかがでしょうか。 いま大事なことは、いたずらに人数の推測を試みることではないと思います。 「実数は知りえない」という事実を受け入れたうえで、定義をめぐる専門的な討議や相談件数の把握など、地道な営みを重ねていくことだと思います。 幸い、これ以上巨大な「人数」を提示しなくとも、ひきこもりは無視できない問題だという共通理解はすでに作られています。 厚生労働省は2000年から、ひきこもりに対する援助の方法を探るための調査を始めました。 18歳以上のひきこもりについていえば、国によるはじめての本格的な取り組みです。 メニュー• Copyright C 2020 All Rights Reserved.
次の